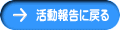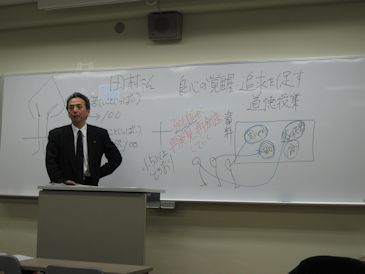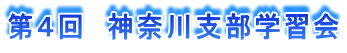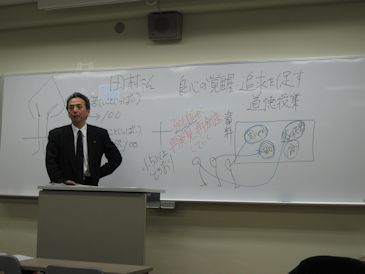
第4回の学習会では、赤坂先生の経験をもとに、子どもから学び、一緒に考え合ってきた道徳教育のあ
り方について、次のようなお話をいただきました。
<道徳教育には、力がある>
○道徳の時間には、価値の内面的自覚をはかるような授業をしなければならない。
そのためには、教師が感動した資料を提示していく必要がある。

<内容にこだわり、多様な方法を用いる>
○教師は、ワンパターンにならないように授業を考えていく必要がある。
普段は、認知面を押さえるためのに、様で幅の広い道徳授業をするが、小学校5年生以上の
子どもたちには時折、「良心の覚醒・追求を促す道徳授業」をしていく。
これは、わざと多くの価値が入っている資料を選び、子ども自らが価値に対して再発見・再創造
していくようにすると良い。
<特別活動の再興を>
○道徳的実践力は、すぐにつけられるものではない。大きくゆったりかまえて、黙々と淡々と行っていく。
普段の授業の中で、感動につながる道徳授業を行っていくことが実践力につながるはず。
○道徳的実践力は、学級活動の中でも培われる。ぜひ、道徳の時間と併せて学級活動の時にも
特に道徳を意識して行ってほしい。

<道徳授業の実効性を性急に求めない>
、○価値を「押しつける」ことと、価値について「教える」ことはイコールではない。
子どもが、人としての在り方を考えるような場面では、ダメなものはダメ、と教えたり、
同時に素晴らしいものと出会わせることが大切になってくる。
○まだ、組織的に道徳教育が成り立っていないところがある。管理職の意識もまだそれほど高くない。
なので、教員一人一人の道徳に対する意識をあげてこれからの道徳教育を支えていくことが
とても重要であろう。