
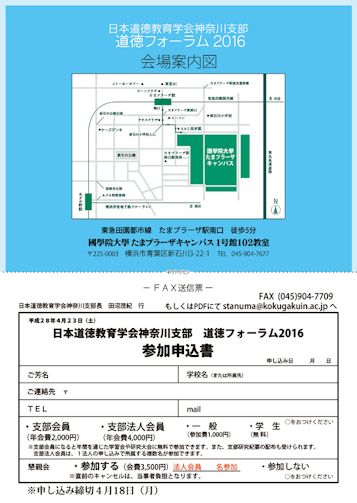
第Ⅰ部 平成28年度総会
①
開会挨拶(田沼支部長)
・神奈川支部も4年目に入り、地域に根付いた活動ができるように なってきた。
なってきた。
・研究紀要には、実践と理論の両方が入っている。今後も工夫した活動を展開していきたい。
・3月27日に、指導要領が一部改正でスタートした。内容と方法論の転換期である。
これからの道徳も少しずつ改善していきたい。
・上廣倫理財団より協力を得ている。今後とも連携をとってよりよい活動をしていきたい。
②
議長選出・・・・・本田理事選出
③
議事
・平成27年度事業報告(森事務局)→承認
・平成27年度会計報告(三井事務局)→承認
会計監査報告(代理神生事務局)
・平成27年度事業計画(案)(森事務局)→承認
・平成27年度予算(案)(三井事務局)→承認
・その他 4/1からの会則の変更について →承認

④
議長解任
⑤
新支部長挨拶及び支部役員の紹介(自己紹介)
⑦
閉会挨拶(根岸理事)
第Ⅱ部 教育実践報告・記念講演
テーマ「今求められる道徳科への課題
~問題解決的な学習で創る道徳教育~ 」
〇思考力をつけなければいけないという考えは、道徳科でも例外ではない。
〇道徳科で問題解決的な学習をどう創っていけばよいのだろうか。
→実際の指導での課題は。
・どのように問題意識をもたせるのか。
・どのような教材を使用するのか。
・どのような指導過程なのか。
・どのように話し合いを組織化していくのか。

② 研究実践発表・・・司会/三ツ木理事
〇「 問題意識から創る主体的な道徳学習への構想
~教師主導から子ども主体の道徳学習へ~ 」
櫻井 雅明 先生 (群馬県藤岡市立鬼石中学校)
・「学習モデルA」・・・導入で問題意識をもつ。問題意識を生み出す。
・「学習モデルB」・・・4人組で話し合いまとめる。
・「学習モデルC」・・・子どもの思いや願いを基に課題を創る。
〇「問題意識をもつ力を養う」ことが大切である。
〇場面設定が身近、印象に残る箇所が一点に集中する資料だと、スムーズな思考の
流れを作りやすい。 →それが、主体的な学習態度につながる。
〇児童の思いから始めるMY道徳は、児童の主体的な活動を促すには有効であろう。

〇「 体験活動との関連を図った道徳の時間 」
南雲 和子 先生 (川崎市立中原中学校)
体験活動と道徳の時間を関連させて一連の学習を組み立てた。
① 地区防災訓練
② 防災講話
③ DIG
④ ミニ道徳 をセットにして流れを組んだ。
道徳の時間では、「生命尊重」を取り上げ、子どもに課題を投げかけた。
価値を一致させることが大切だと、改めて感じた。

③ 記念講演
「今求められる道徳科への課題
~問題解決的な学習で創る道徳教育~ 」
講師 柳沼 良太 先生
(岐阜大学大学院教育学研究科准教授
/中央教育審議会道徳教育専門部会委員)
これからの社会で求められる能力は、答えのない問題に最善解を導ける能力である。
そのためには、教師中心の授業から、子ども中心の授業にしていかなければならない。
従来の道徳授業は、わかり切ったことを言わせたり書かせたり、現実問題に対応できなかったりと
学年があがるにつれて、子どもの受け止めがよくないものだった。
自分ならどのように行動・実践するかを考えさせ、自分とは異なる意見と向かい合い議論する中で
道徳的価値について、多面的・多角的に学び、実践へと結びつけ、更に習慣化していく指導へと転換
することこそ、道徳の教科化の大きな目的である。
例えば、このような道徳の授業にしていくことが考えられる。
・対立する見解を考え議論する。
・道徳的価値をどうすれば獲得できるかを考える。
・「どんな気持ちか」だけではなく、「何をすべきか」「なぜそうすべきか」「自分ならどうするか」を問う。
・「あれか、これか(オープンエンド)」ではなく、第3、第4の道を考える。(最善策)
・「そうしたらどうなると思いますか。(結果)」を問う。
・「いつ、どこで、誰にでもそうするか?」「それで皆、幸せになれるか?(多面的・多角的)」を考える。
・全員が参加できるしかけや体験的な学習を考える。
(2~4人で話し合う)(役割演技 ペア→みんなの前で)(別の場面のシュミレーションをしてみる)
いずれにしても、教師のアドリブ力が肝心であると同時に、子どもたちの「自他を尊重し、聞き合う関係」
が前提になるだろう。

④ 閉会挨拶(星野副支部長)
